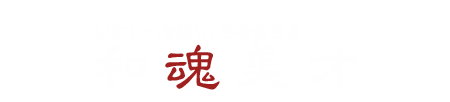戦争論といえばクラウゼヴィッツの大作が有名ですが、これは評論家・マンガ家の小林よしのり氏のものです。大東亜戦争(先の大戦)について、徹底して肯定論の立場からストーリーを描いているのが特長です。「戦争は悲惨さのみを描くべき」「敗戦国は正義をとり戻せない」といった固定観念に縛られた人が一読すると多くの発見があると思います。
勝ち戦の物語は気分がいいものですが、負け戦の物語は気分が重くなる物です。日露戦争の物語はよくドラマになります。これは勝ち戦なのでハッピーエンドにしやすいからです。対して、大東亜戦争は日本の圧倒的な負け戦だったので、気分のよい物語にはしにくいテーマです。ただ、そこをあえてやった所によしりんの戦争論の希少性があります。
東京裁判的な歴史観、つまり「明治~昭和初期の日本帝国は悪の帝国だった」的な一方的な歴史観に無意識に毒されている人にとっては、よしりんの戦争論は非常に優れた解毒剤になることでしょう。
負け戦の話は悲惨な話ばかりなので気分が悪い物ですが、実際は気分が重い中にも感動的な物語はあります。一例は、「硫黄島の戦い」です。
この戦いについては、クリント・イーストウッドが米軍側・日本軍側の双方の視点にたった非常に公正な映画を制作してくれていますので、一度観覧しておくことを勧めます。アメリカ視点の作品 「父親達の星条旗」と日本視点の作品の「硫黄島からの手紙」があります。一方的ではない広い視点にたった歴史観を養うという意味で非常に役に立ちます。(アメリカ人が作ったとは思えない出来映えです)
史実の硫黄島の日本軍は米軍に対して圧倒的に不利な状況の中で、死力を尽くして1ヶ月の間、防衛戦を戦い抜き、米軍に対して自軍よりも多くの損害を与えるという結果を残しています。「5日で攻略可能」と予測していた米軍は、1ヶ月の死闘を味わうことになります。
「絶望的な状況にあっても、最後の最後まで死力を尽くす(自殺は禁止。死ぬまで諦めずに戦う)」 という人間精神のすさまじさがそこにはありました。
硫黄島の戦闘が激戦になった理由ですが、硫黄島が米軍による日本列島空襲のための 重要な戦略拠点になる場所にあったのが大きな理由です。日本側からすると、この島の 陥落は米軍による本土空襲の激化を意味していました。
人間には誰しも「こんな暗い日々が続くくらいなら、死んだほうがましだ」と感じる瞬間があると思います。そういう時は、文字通り「最後の最後まで戦い抜いて死んでいった人達の記録」にふれると、畏敬の念と供に勇気がわいてくることでしょう。勇戦虚しく死んでいった兵士たちの物語にふれることは「自分自身の死について考える(メメント・モリ)」上でも非常に有意義な時間になります。